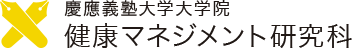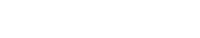修士(スポーツマネジメント学)

養成する人材像
個人や集団の健康の維持・増進に資する知識とビジネスマネジメント技能を統合することによって、健康水準の高い社会のあり方を企画・実践でき、スポーツ文化の振興とスポーツ産業の発展に貢献できる人材を育成することを目的としています。
スポーツの捉え方
定期的にカラダを動かすこと(身体活動)に健康効果があることは、広く知られています。身体活動(physical activity)は、安静にしている状態より多くのエネルギーを消費するすべての身体の動きと定義され、仕事中の身体活動、移動中の身体活動、余暇の身体活動などに分類されることがあります。余暇の身体活動には、運動(exercise)やスポーツ(sports)が含まれます。運動は体力の維持・向上などを目的として計画的・意図的に実施される身体活動(例えば、ウォーキングやジョギングなど)、スポーツは共通ルールの下で相対的に高度な技能をもって競争を伴い行われる身体活動(例えば、テニスやサッカーなど)と定義されます。昨今では、階段昇降のような身体活動まで含めて、スポーツを広義に捉えることが一般的になっています。
スポーツをスポーツ医科学の観点から捉えれば、「強度」「時間」「頻度」から構成されるものとなります。スポーツ社会学の観点からは、「時間」「空間」「仲間」という3つの「間」から構成されるものとして捉えることができます。スポーツ経営学の観点からは、「消費財」という従来的な位置づけにとどまらず、「投資財」や「公共財」としても位置づけることができます。また,スポーツの根源が「遊び」であることの理解も重要です。
本プログラムの特徴
本プログラムでは、インターンシップの実施あるいは研究プロジェクトへの参加に基づく課題研究論文に取り組むことが推奨されます。現場の課題を解決するために、科学的手法に基づき事例分析を丁寧に行い、改善策立案や政策提言を行うことが期待されます。
運動生理・スポーツ外傷・障害予防・リハビリテーション
「スポーツが健康によい」といっても、過度・過剰であれば健康を害することもあります。適度な強度のスポーツであっても、こまめな水分補給や休憩を怠れば、熱中症になって健康を損ねることもあります。スポーツと医学は相互補完的な関係にあり、スポーツと医学の双方向性を理解することで、運動や身体活動の意義をより科学的に捉えることができます。身体活動・運動に伴う身体の機能・構造の変化の現象と仕組みといった基礎理論(運動生理学、整形外科・リハビリテーション領域の理論)や、身体機能や身体組成の評価方法など、スポーツに携わる者には最低限のスポーツ医学の知識の習得が求められます。
スポーツ科学
スポーツを取り巻く環境は大きな進化を続けています。アスリートのパフォーマンス向上に資するビッグデータの解析はコーチングやトレーニングの方法を革新的に変え、工学知識を生かした生体データの開発や取得はコンディショニング管理やリカバリー戦略を「見える化」することに貢献しています。このように、スポーツを科学する研究分野では、基盤となる運動生理学やバイオメカニクス、トレーニング科学にデータサイエンスなどが融合することで新たな価値が生み出されています。スポーツ科学の対象は、一般市民の日常的な身体活動や動作の計測・評価にも広がっています。例えば、ウェラブルデバイスを活用した健康管理や、加齢に伴う運動機能の変化を分析する研究などが進められており、こうした知見は健康増進や介護予防の分野にも応用されています。スポーツ科学で得られた知見をアスリートのパフォーマンス向上からず国民の健康増進まで幅広く活用するためには、科学的根拠に基づき、論理的に思考される学際的な知識と行動が求められます。
スポーツによる健康増進
健康課題はライフステージに応じて変化します。例えば、壮年・中年期にはメタボリックシンドローム、高年期にはロコモティブシンドロームやフレイルが健康上の課題となります。こうした健康課題への対策として定期的な身体活動が有効であることは、数多くの科学的根拠(エビデンス)によって示されています。しかし、単にエビデンスを示しただけでは、定期的な身体活動の定着にはつながりません。intrapersonal(個人内)、interpersonal(個人間)、community(コミュニティ)という異なるレベルへどのようにアプローチするか、基礎理論を身に付け、社会実装へつなげる企画力・実践力を備えた人材の育成が求められます。
スポーツの成長産業化
『レジャー白書』(日本生産性本部)によれば、スポーツ市場は、1992年に6兆を超える規模にまで拡大したのち減少基調に転じ、2011年には4兆円を割り込みましたが、規模縮小に歯止めがかかり、コロナ禍を経て、回復・成長の兆しがみえる状態にあります。第3期スポーツ基本計画(スポーツ庁)では、施策目標のひとつとして、スポーツ市場の規模拡大が掲げられています。スポーツ産業が拡大・発展するために克服すべき課題として、マネジメント系人材の不足が指摘されています。スポーツという商品の特性を理解し、マネジメント理論や科学的分析手法を身につけた人材、すなわち、ロジカルに戦略を練りエモーショナルにスポーツの価値を訴求できる人材の育成が求められます。
スポーツ医学研究センター・体育研究所との連携
スポーツマネジメントでは、スポーツ医学研究センターならびに体育研究所と緊密に連携しながら、学生の教育を行う体制を整えています。スポーツ医学研究センターの業務活動(塾体育会所属アスリートのサポート活動等)や研究プロジェクト(藤沢市民を対象とした身体活動促進活動やウェアラブルセンサーを用いた動作解析等)に参加することで、実務経験を積みながら、プロジェクトに関連した課題研究に取り組むことができます。
モデルカリキュラム
健康マネジメント研究科では多様な授業科目が提供されています。修了要件を充足すれば、授業科目の履修選択は自由です。モデルカリキュラムは、履修選択する際の一助となるよう、研究領域別に作成されています。したがって、モデルカリキュラムは履修選択を拘束するものではありません。また、実際の履修にあたっては、必修科目や必要単位数などの修了要件を確認したうえで履修科目を選択していただく必要があります。あくまで参考資料としてご参照ください。